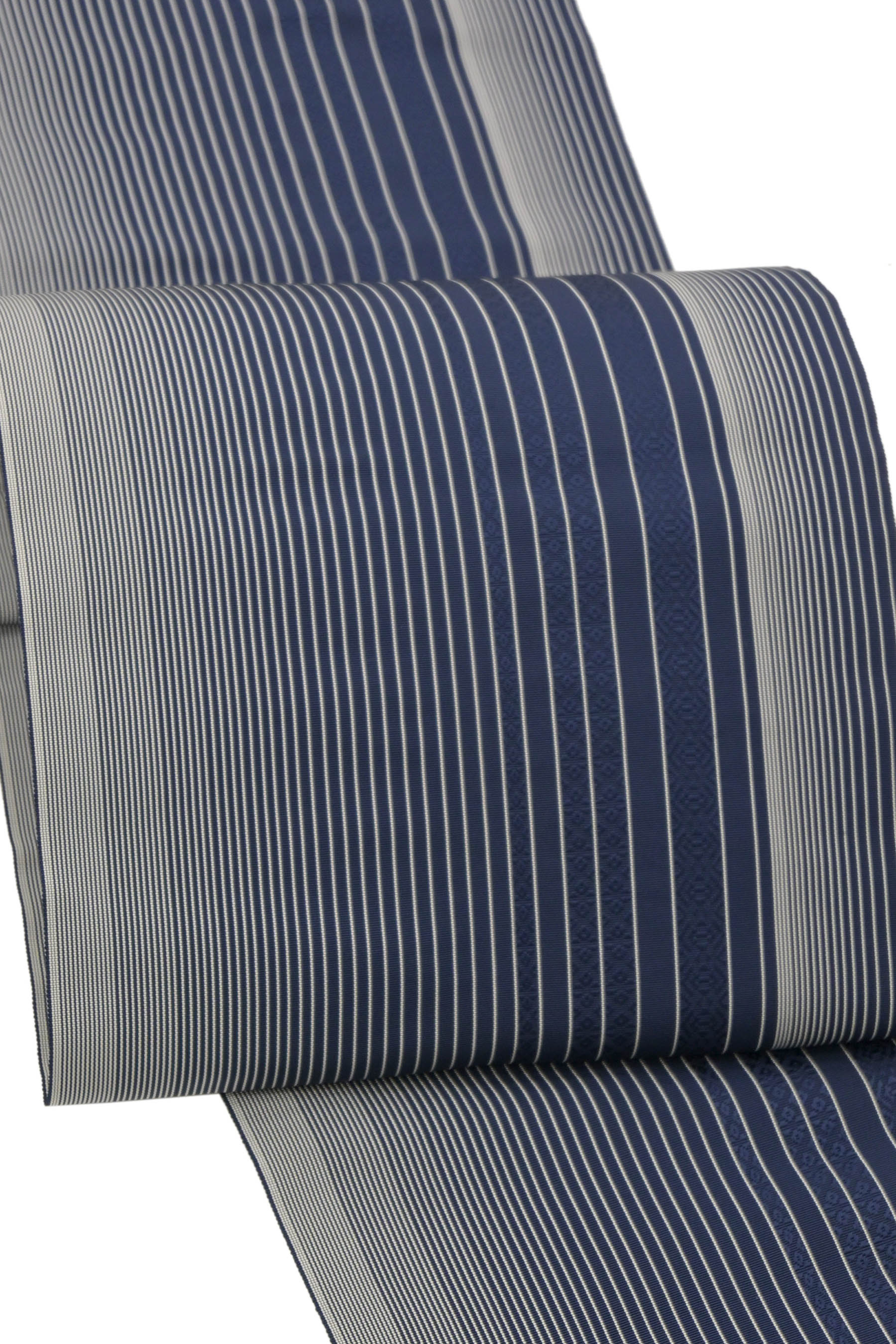- 50音選択に戻る
- 50音選択に戻る
- 50音選択に戻る
- 50音選択に戻る
- 50音選択に戻る
- 50音選択に戻る
- 50音選択に戻る
- 50音選択に戻る
- メニューに戻る
- メニューに戻る
- メニューに戻る
- メニューに戻る
メニューに戻る
-
メニューに戻る
- 店舗情報
商品番号:1559916
(税込)
(税込)
【 仕入れ担当 中村より 】
またひとつ、終わりを告げる日本の伝統技。
井上久人氏。80歳をこえられた現在、
世に素晴らしい作品を残し続けた井上氏は、
残念ながら引退されたそうです。
機械織にはない手織りのぬくもり、しなやかさ、ハリ…
伝統工芸士・井上久人氏が、この道ひとすじに培われた技で、
心を込めて織り上げた特選品をご紹介致します。
もちろん現品限りでございます。
どうぞお見逃しなく!
【 色・柄 】
手織りと織機の違いはなんなのか。
まず圧倒的に打ち込みの回数が違います。
織機であれば緯糸を通す器具、杼(シャトル)が一度通るごとに緯糸を筬で手前に打ち込み、織り上げていきます。
この筬で打ち込む回数が織機は一回に対し、手織りの場合は、織機と織手が一体となり、自ら杼を一度通すごとに緯糸を筬で約六回、
「カカン、カン、カン、カン、カン!」といったリズムで、実に力強く打ち込むのです。
その差は締めるごとに出てくるといいます。
手織りの博多八寸帯は、いついつまでも、そのしっかりとしたシャリ感、絹なり、
風合いが損なわれることなくお締めいただけます。
しなやかなハリのある博多織特有の打ち込みの帯地。
深い紺色を基調として
独鈷文を込めた変り縞献上模様が織りなされました。
伝統の美しい文様を忘れずに、洗練されたデザインは、
豊かな品格を演出してくれます。
【 商品の状態 】
中古品として仕入れてまいりましたが、
大切に保存されていたのでしょう、美品でございます!
お手元で現品を確認の上、お値打ちにお召しくださいませ!
【 博多織について 】
経済大臣指定伝統的工芸品(1976年6月14日指定)
鎌倉時代、中国(南宋)へ渡った商人の
満田弥三右衛門が考案し、その子孫が改良工夫して
博多に広めたとされる。
博多織による帯を筑前黒田藩の初代藩主・黒田長政が
江戸時代に幕府に献上したことで広く認知された。
これによりその図柄には献上柄と名がついた。
現在の博多織の献上柄には厄除け、子孫繁栄、
家内安全の願いが込められている。
1本の帯を作るのに7000~15000本もの経糸を使うため
柔らかくてコシのある地風である。
糸の密度が高いので締める時にキュッキュッという
「絹鳴り」と呼ばれる独特の音色がする。

絹100%・金属糸風繊維除く
長さ約3.7m
柄付け:全通柄
◆最適な着用時期 9月の単衣から翌6月までの単衣、袷(あわせ)の時期
◆店長おすすめ着用年齢 ご着用年齢は問いません
◆着用シーン 和のお稽古、芸術鑑賞、観劇、ご友人との気軽なお食事 など
◆あわせる着物 色無地、小紋、御召 など
※仕立て上がった状態で保管されておりましたので、折りたたみシワがついております。この点をご了解くださいませ。