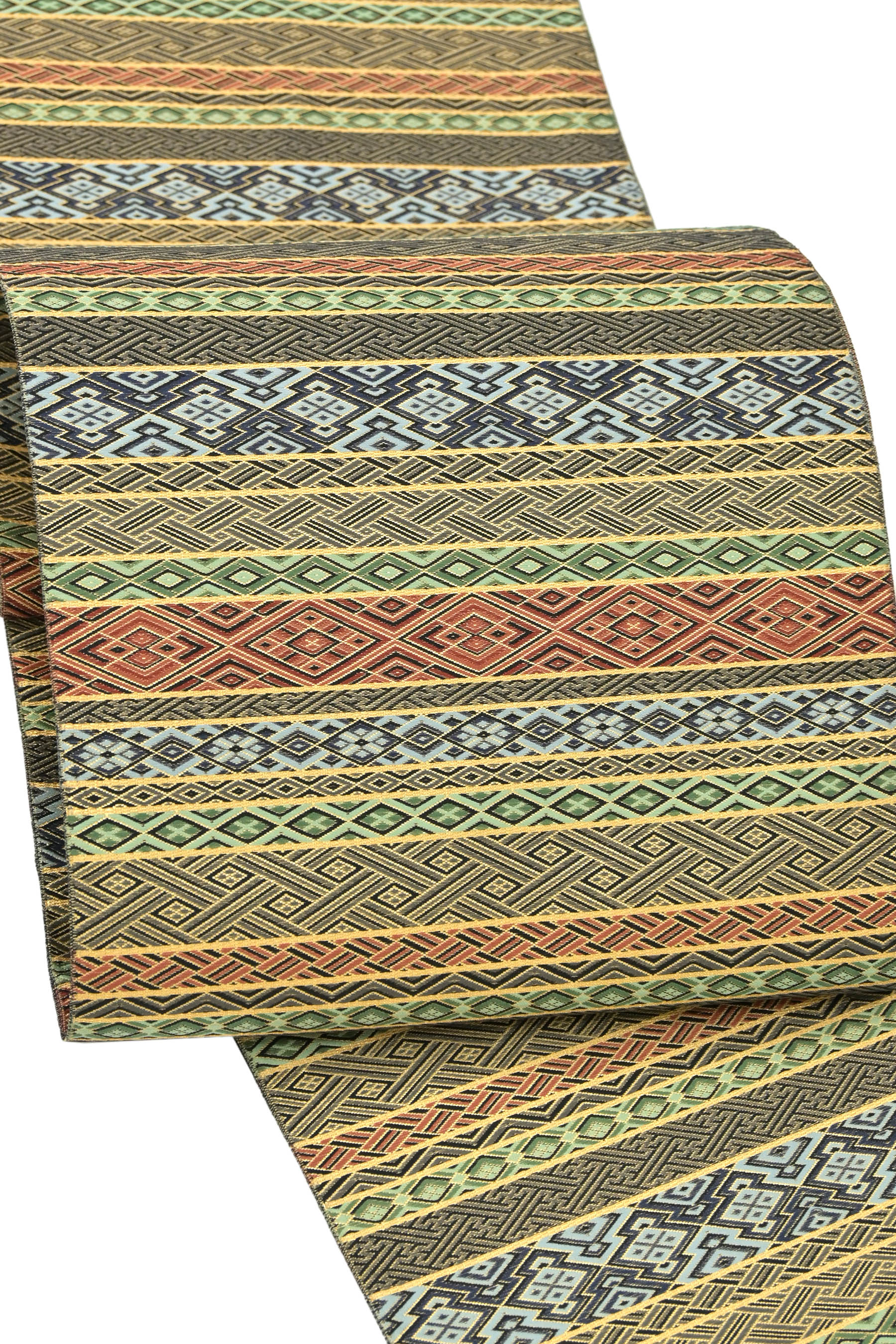- 50音選択に戻る
- 50音選択に戻る
- 50音選択に戻る
- 50音選択に戻る
- 50音選択に戻る
- 50音選択に戻る
- 50音選択に戻る
- 50音選択に戻る
- メニューに戻る
- メニューに戻る
- メニューに戻る
- メニューに戻る
メニューに戻る
-
メニューに戻る
- 店舗情報
商品番号:1546419
(税込)
【 仕入れ担当 渡辺より 】
時代を超えて愛されるその織味…
しなやかでしめやすく、体になじむその風合い。
きもの雑誌などにも掲載されたことのある
【 小森草木染工房 】による希少な佐賀錦袋帯のご紹介です!
煌びやかなフォーマル帯といえば、
どうしても硬く締めにくいものが多いですが、
やはり博多帯、締めやすさは抜群です!
八寸帯が主流の博多織。
袋帯は生産数も絶対的に少なく、
ましてや佐賀錦の袋帯ともなりますと、
大変珍しく、また新品では大変高価に取引されております。
御仕立て上がりならではのお値打ち価格でご紹介しますので、
お目に留まりましたら是非ともお見逃しなく!
【 お色柄 】
やわらかくしなやかに織り上げられた帯地。
経糸の箔糸がほのかに煌めくその地には、
優彩のお色使いにて松皮菱などをモチーフとした
幾何学的な菱模様を横段に織りあげました。
博多織ならではの裏地にもこだわった仕上がり。
裏地屋のない、博多織では裏生地も表地と同様、
博多織にて織り上げられることとなり、
そのため、安価に出回ることがないのです。
その分締め心地の良さも格段に上がり、
締めやすくシワになりにくいという利点も。
そういった点も、お着物好きの方から愛される所以でございましょう。
日本独自の文化の中で、受け継がれてきた豊かな感性と洗練された
確かな美意識界を自信をもっておすすめ致します。
お手元でご愛用いただけましたら幸いでございます。
【 商品の状態 】
中古品として仕入れて参りました。
薄っすらと締め跡がございますがおおむね良好です。
お手元に届いてすぐにお召しいただける状態でございます。
【 小森久について 】
博多織の染織作家
小森草木染工房主宰
1928年 筑前秋月(福岡県甘木市)生まれ
父親がもともと博多織職人で久も父親と同じ道を歩む。
博多織職人として働いていたが、戦後着物織りの
需要がなくなり、一時は木炭を焼く仕事で生計を
立てていた。
その木炭制作の合間に感じた自然への思いを切欠に、
山などに自生する材料を用いた染色の研究を開始。
その後60年以上、自然由来の材料で生地を染める
草木染の研究と創作活動にその生涯を捧げる。
後に「本・草木染」と名付けられた技術は、
1975年に地元である甘木市の無形文化財に指定され、
全国各地の織物品評会でも数々の大賞を受賞した。
小森久の「本・草木染」で使用される植物は、
一般的な草木染でも用いられる藍・茜・山桜をはじめ、
その種類は160種類にのぼる。
【 博多織:佐賀錦 について 】
肥前鹿島藩の御殿女中に受け継がれた織物。
京都・西陣織など一般的な織物は箔を緯糸に用いるが、
佐賀錦は箔糸(金銀箔を漆で和紙に貼り細く切ったもの)
を経糸とし、絹糸を緯糸にするほか、織機ではなく
織り台という小さな台に糸や箔をかけて独自の
道具を用いて織るのが特徴。
本来の佐賀錦は織り台を用いるが、現在は
通常の経糸と緯糸に絹糸を使用する博多織と区別し、
絹糸と箔(金色や銀色や焼き箔など)を使用したものを
佐賀錦と呼んでいる。
絹糸は、形状が丸なので上下がないが、箔の場合
張力などが異なるので、耳の引き具合や打ち込み、
箔糸の返りを確認しながら製織せねばならず、
熟練の職人でなければ製織できない。
絹100%・金属糸風繊維除く 長さ約4.6m(長尺)
柄付け:全通柄
耳の縫製:かがり縫い
◆最適な着用時期 10月~翌年5月の袷頃
◆店長おすすめ着用年齢 ご着用年齢は問いません
◆着用シーン パーティー、お付き添い、観劇、お食事会など
◆あわせる着物 訪問着、付下げ、色無地など
※仕立て上がった状態で保管されておりましたので、折りたたみシワが付いております。この点をご了解くださいませ。
この商品を見た人はこんな商品も見ています