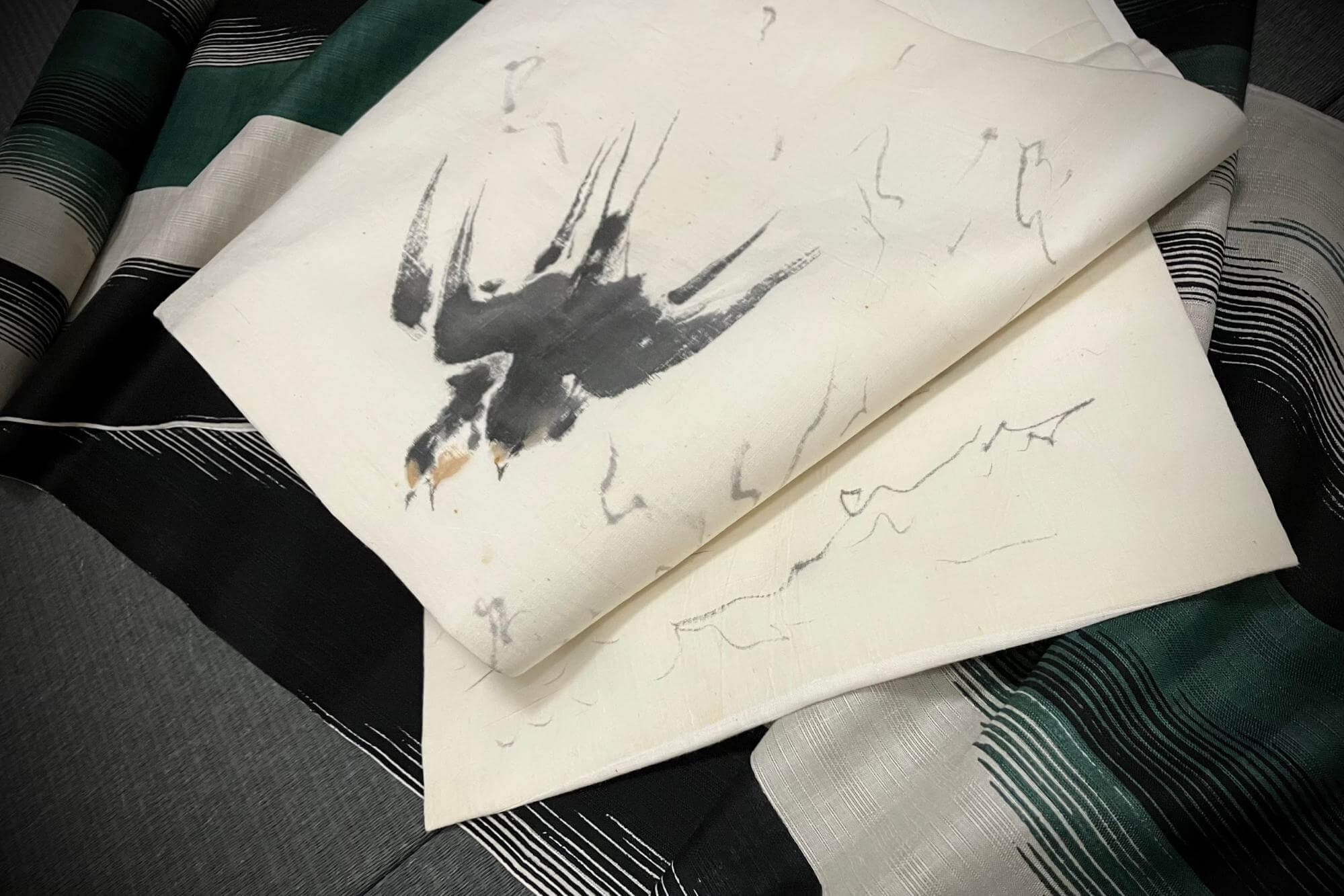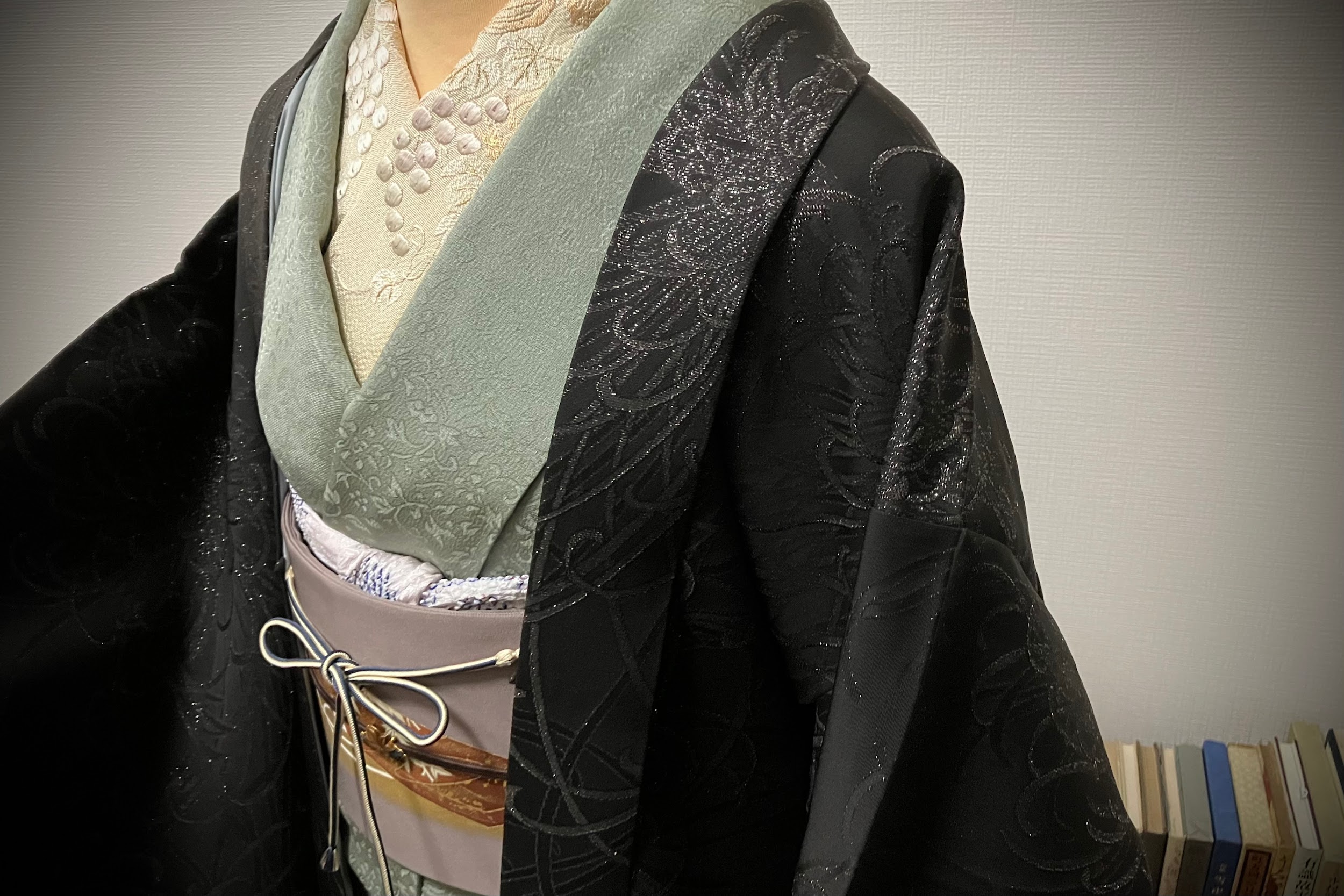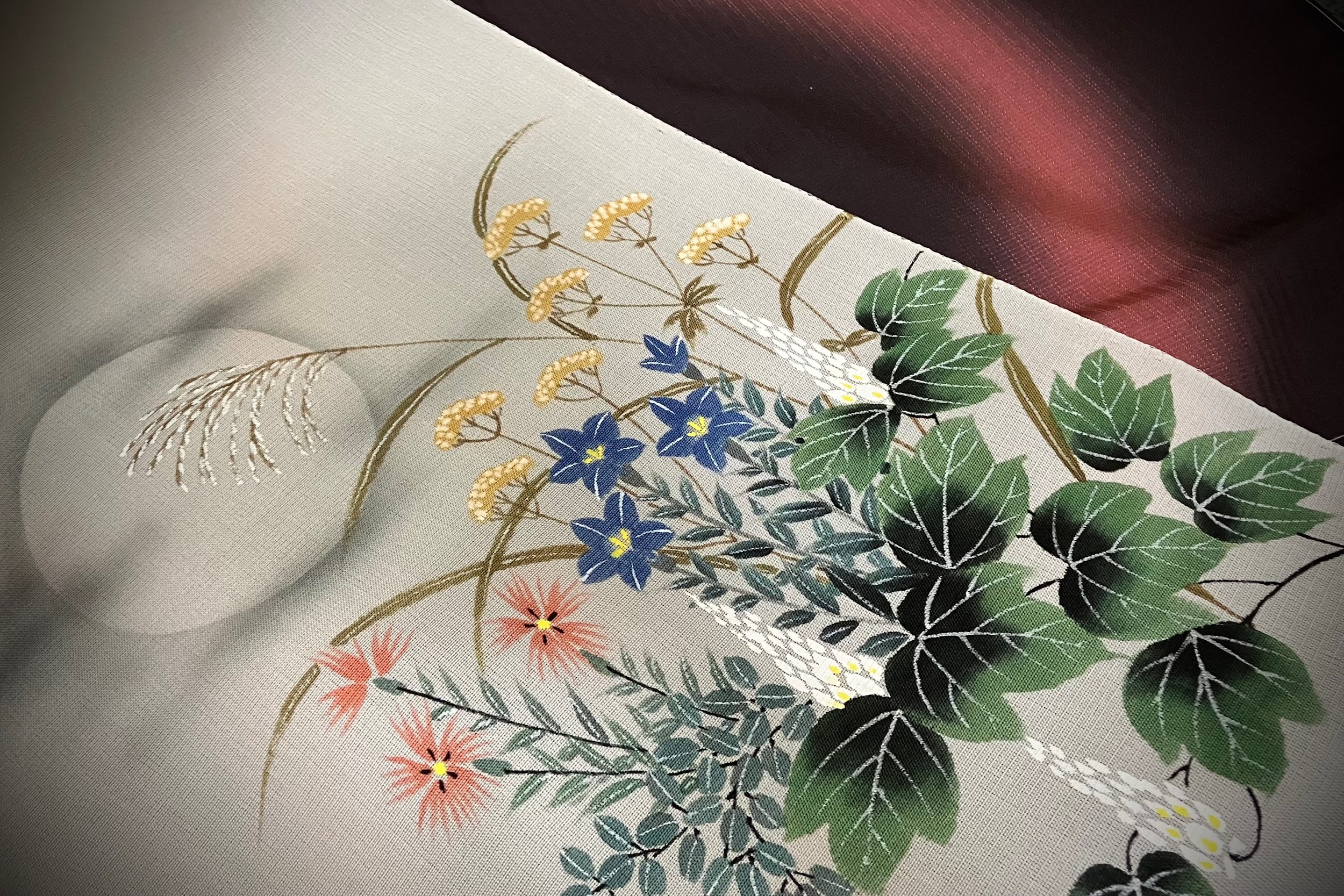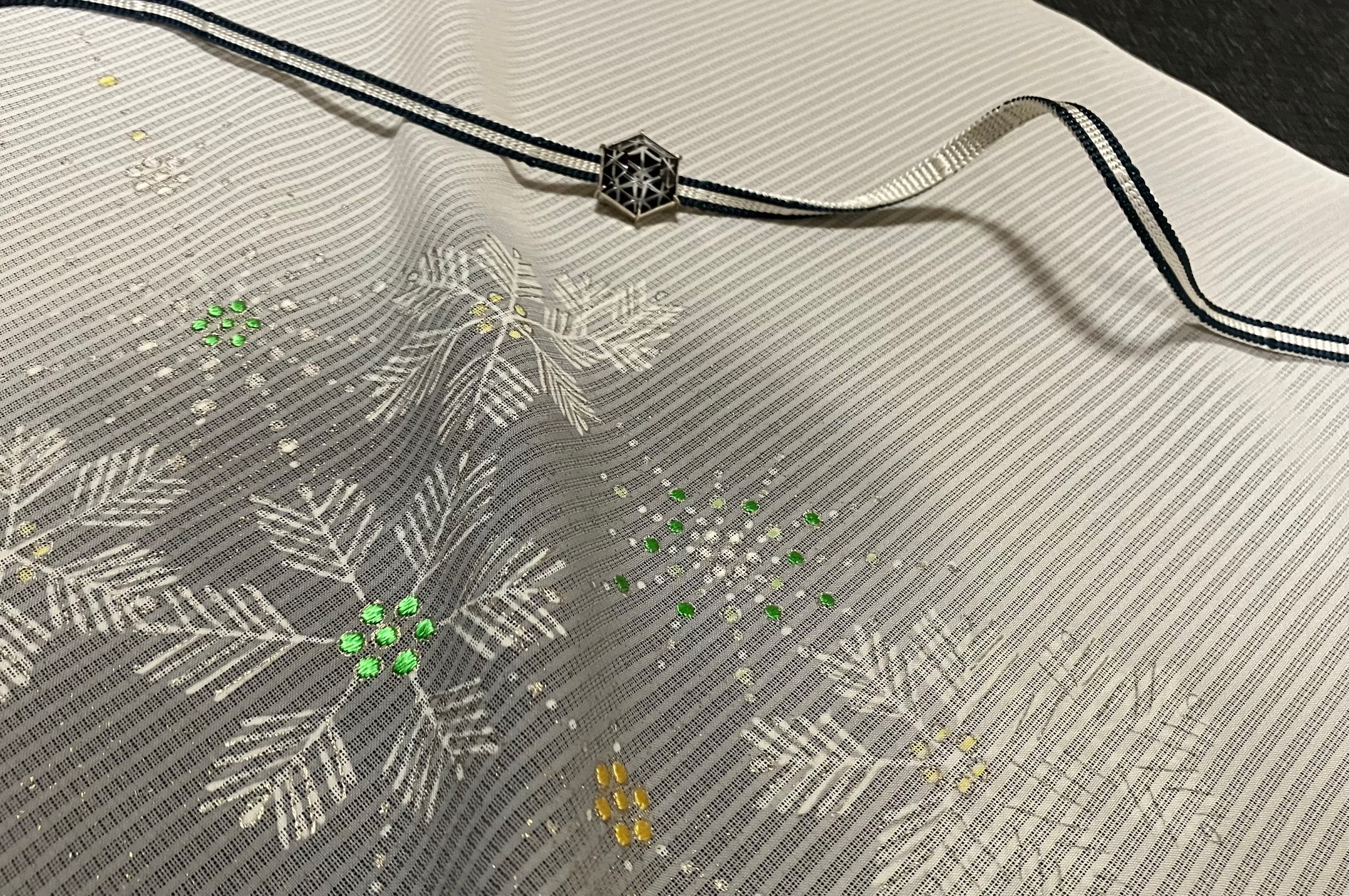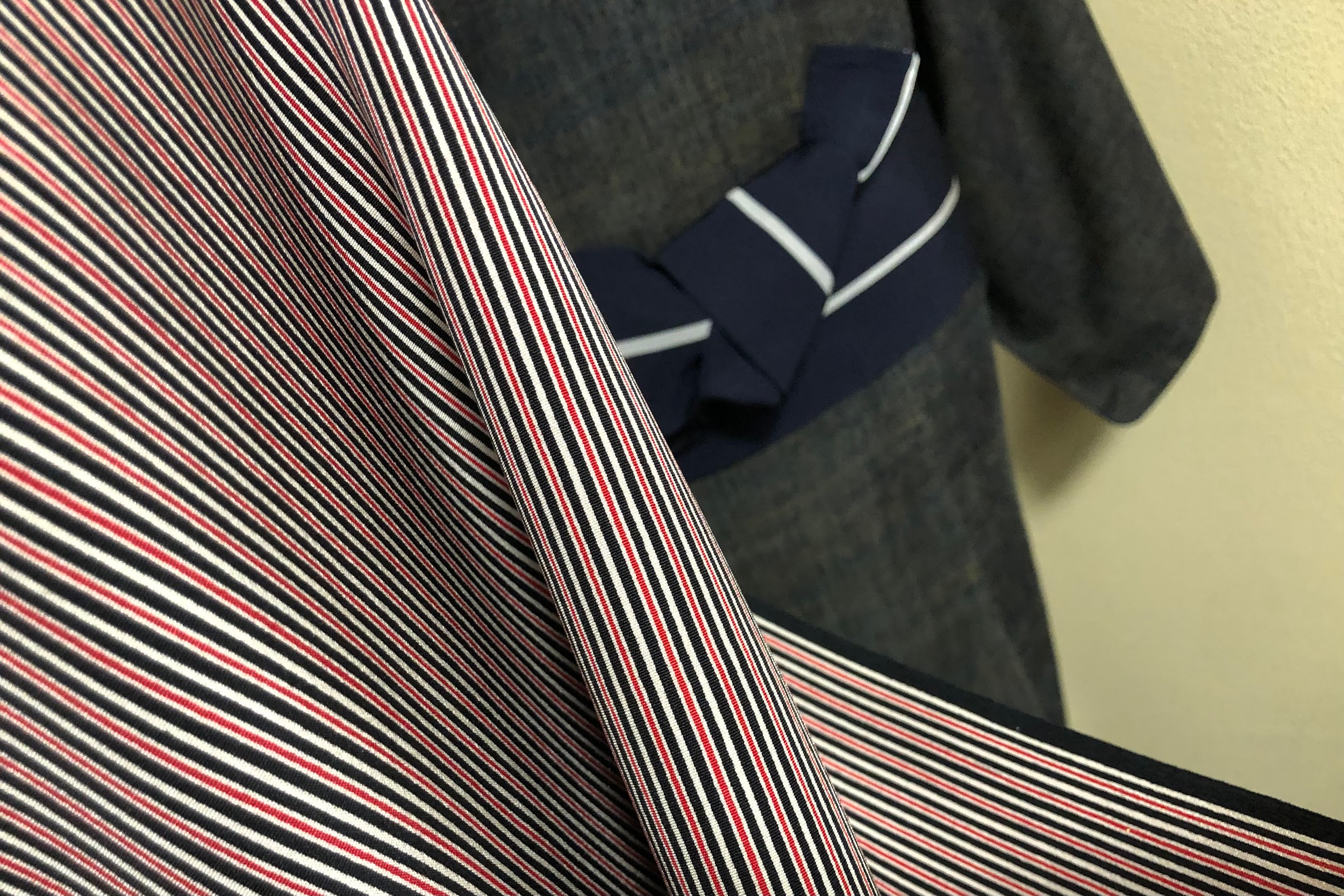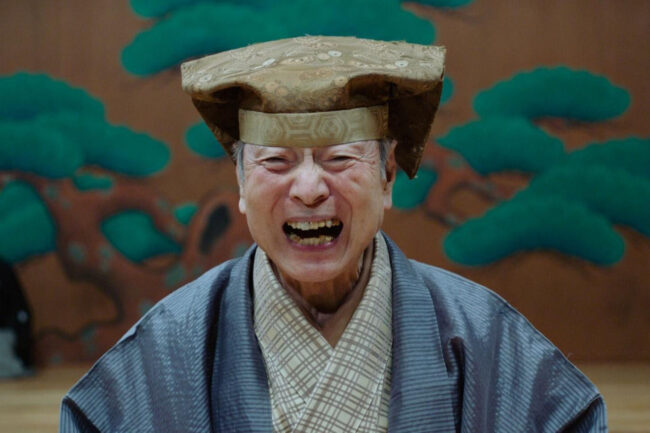あえかな月の光のような 〜小説の中の着物〜 杉本章子『東京新大橋雨中図』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第五十夜
小説を読んでいて、自然と脳裏にその映像が浮かぶような描写に触れると、登場人物がよりリアルな肉付きを持って存在し、生き生きと動き出す。今宵の一冊は、杉本章子著『東京新大橋雨中図』。蛇の目傘、縞の着物、紅の蹴出し―――激動の時代ー明治維新ーに翻弄され、過酷な運命に殉じた女(ひと)への哀慕の念を礎に、もと幕臣の小林清親が世に生み出したのは、移ろいゆく光と影を描いた新たな浮世絵「光線画」。「最後の木版浮世絵師」と呼ばれた清親が描く、あえかな月の光のような優しさと哀しみを湛えた世界を、“お江戸のにおい”とともに。
目次
シェア
BACK NUMBERバックナンバー
-

2025.08.27
連載記事
あえかな月の光のような 〜小説の中の着物〜 杉本章子『東京新大橋雨中図』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第五十夜
-

2025.08.16
連載記事
色彩と陰影を纏う 〜小説の中の着物〜 夏目漱石『三四郎』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十九夜
-

2025.07.28
連載記事
愛嬌も芸のうち 〜小説の中の着物〜 吉川潮『浮かれ三亀松』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十八夜
-

2025.07.30
連載記事
装いは演出、そして武装 〜小説の中の着物〜 菊池寛『真珠夫人』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十七夜
-

2025.07.28
連載記事
袙扇のうちとそと 〜小説の中の着物〜 阿岐有任『籬の菊』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十六夜
-

2025.07.28
連載記事
紫色の白昼夢 〜小説の中の着物〜 泉鏡花『艶書』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十五夜
-

2025.07.06
連載記事
陽の当たる、その裏で 〜小説の中の着物〜近藤史恵 『散りしかたみに』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十四夜
-

2025.07.06
連載記事
其処ではすべてが露呈する〜小説の中の着物〜 澤田ふじ子『宗旦狐ー茶湯にかかわる十二の短編ー』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十三夜
-

2024.11.03
連載記事
踊る女と傾く男 〜小説の中の着物〜 天野純希『桃山ビート・トライブ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十二夜
-

2025.07.06
連載記事
憂いの黒羽織 〜小説の中の着物〜 樋口一葉『十三夜』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十一夜
-

2025.07.06
連載記事
誰かのためだけの、ただひとつのもの 〜小説の中の着物〜 知野みさき『神田職人えにし譚』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十夜
-

2025.07.06
連載記事
闇に咲く花 〜小説の中の着物〜 泉ゆたか『髪結百花』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十九夜
-

2025.07.06
連載記事
夏の夜の幻想に酔う 〜小説の中の着物〜 皆川博子『ゆめこ縮緬』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十八夜
-

2025.07.06
連載記事
溺レル幸福 〜小説の中の着物〜 谷崎潤一郎『痴人の愛』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十七夜
-

2025.07.06
連載記事
あをによし 〜小説の中の着物〜 永井路子『美貌の女帝』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十六夜
-

2025.07.06
連載記事
日々はそうして過ぎていく 〜小説の中の着物〜 木内昇『浮世女房洒落日記』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十五夜
-

2025.07.06
連載記事
節目の白絹 〜小説の中の着物〜 津村節子『絹扇』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十四夜
-

2025.07.06
連載記事
美しい手の引力 〜小説の中の着物〜 蜂谷涼『雪えくぼ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十三夜
-

2025.07.06
連載記事
徒花は咲き誇り、我が道をゆく 〜小説の中の着物〜 山崎豊子『ぼんち』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十二夜
-

2025.07.06
連載記事
働くことは生きること 〜小説の中の着物〜 朝井まかて『残り者』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十一夜
-

2025.07.06
連載記事
“かたい”着物で護るものは 〜小説の中の着物〜 立原正秋『舞の家』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十夜
-

2025.07.05
連載記事
掌(たなごころ)を充たすものー装幀という芸術ー 〜小説の中の着物〜 邦枝完二著『おせん』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十九夜
-

2025.07.05
連載記事
愛おしき小さなものたち 〜小説の中の着物〜 畠中恵著『つくもがみ貸します』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十八夜
-

2025.07.05
連載記事
雪が模様になった日 〜小説の中の着物〜 葉室麟著『オランダ宿の娘』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十七夜
-

2025.07.05
連載記事
羅(うすもの)や 〜小説の中の着物〜 瀬戸内寂聴著『いよよ華やぐ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十六夜
-

2025.07.05
連載記事
宵闇に、白地のゆかた 〜小説の中の着物〜 宇野千代著『おはん』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十五夜
-

2025.07.05
連載記事
女たちは、それぞれの生を生きた 〜小説の中の着物〜 松井今朝子『円朝の女』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十四夜
-

2025.07.05
連載記事
蒐集という甘い毒 〜小説の中の着物〜 芝木好子『光琳の櫛』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十三夜
-

2025.07.05
連載記事
滅びの夢の、その先の 〜小説の中の着物〜 久世光彦『雛の家』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十二夜
-

2025.07.05
連載記事
“粋”と“品”の本質 〜小説の中の着物〜 宇江佐真理『斬られ権佐』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十一夜
LATEST最新記事
-

ファッション
あえかな月の光のような 〜小説の中の着物〜 杉本章子『東京新大橋雨中図』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第五十夜
-

ライフスタイル
着物の所作を美しくするために重ねた訓練【女優 熊谷真実さん】(後編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.8
-

カルチャー
遊郭は江戸のセーフティネット? 「知ってた?べらぼうなお江戸話」vol.2
-

ライフスタイル
【おとめ座】『ざざんざ織』を着回すコーデ 「12星座で実践!着物1枚に帯3本」vol.1
-

カルチャー
人間国宝・野村万作氏の狂言に捧げた90年『六つの顔』 「きもの de シネマ」vol.68
-

インタビュー
【対談】映画作家 河瀨直美さん×着物家 伊藤仁美さん ――着物はひとりで着るものじゃない。
RANKINGランキング
- デイリー
- ウィークリー
- マンスリー
-

着物の基本
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

ライフスタイル
若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.7
-

カルチャー
幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6
-

カルチャー
”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20
-

エッセイ
きものの収納、どうしてますか? 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.30
-

イベント
女性職人がえがく「江戸の粋」 石塚染工5代目・石塚久美子さんの江戸小紋 in 京都きもの市場・銀座店
-

エッセイ
ラクに着る!着物×洋装ミックスコーデ「3兄弟母、時々きもの」vol.7
-

エッセイ
蒐集という甘い毒 〜小説の中の着物〜 芝木好子『光琳の櫛』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十三夜
-

エッセイ
源氏物語のもう一人の主役、紫の上 「源氏物語の女君がきものを着たなら」vol.1
-

ライフスタイル
若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.7
-

着物の基本
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

ライフスタイル
桜花祭で織姫 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.4
-

カルチャー
投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5
-

ライフスタイル
端午の節句に菖蒲尽くし 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.5
-

着物の基本
今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味
-

ライフスタイル
萬燈会とお盆飾り 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.8
-

エッセイ
9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75
-

着物の基本
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

着物の基本
着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!
-

カルチャー
”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20
-

着物の基本
今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味
-

着物の基本
しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5
-

カルチャー
投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5
-

ライフスタイル
若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.7
-

着物の基本
兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!
-

着物の基本
初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!
-

着物でおでかけ
特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49